最初の段階が一番楽しい
──では一番楽しいと思うことは?
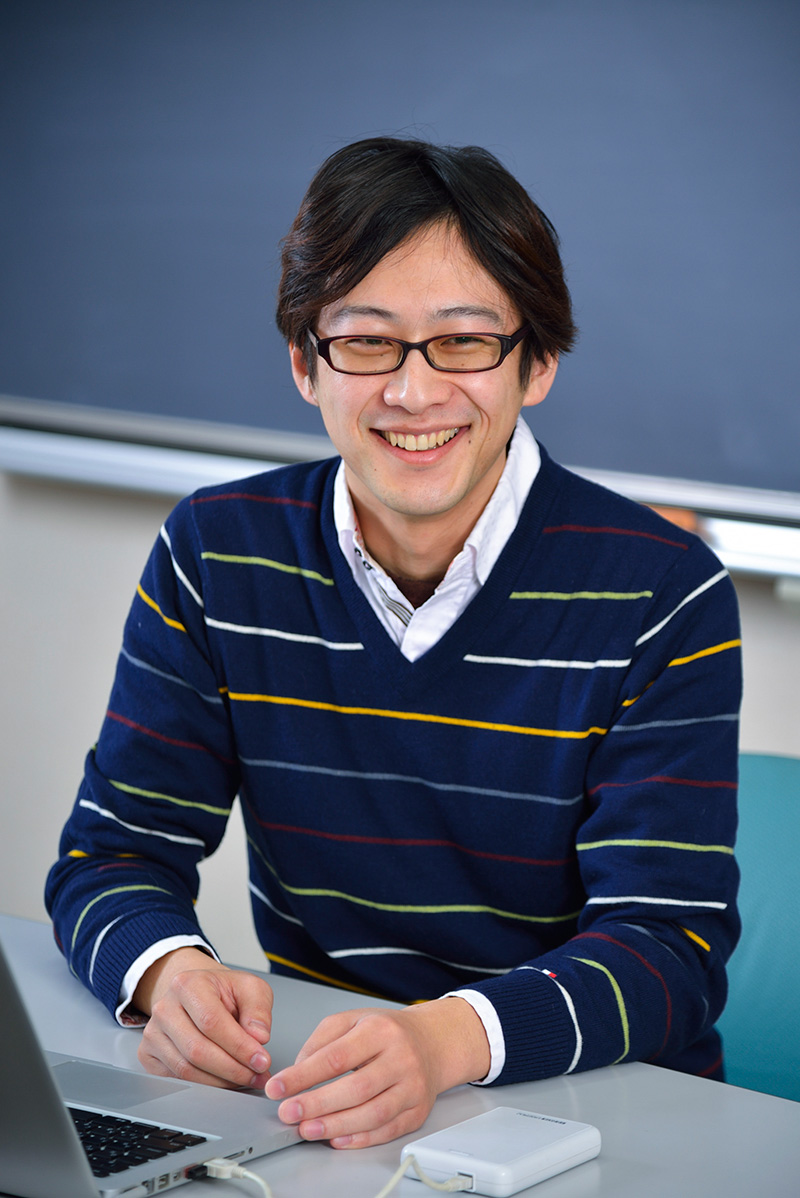
私の感覚としては、KSELのイベントまでのフェーズは企画構想段階と準備段階と本番当日に大きく分けられます。その中で、最初の構想段階、これをやったらおもしろそうだな、もっとこんなこともできるかもしれない、と妄想をふくらませているときが一番楽しいですね。
逆に一番たいへんなのはイベント直前の準備段階です。お客さんを喜ばせるために万全の準備を整え、あらゆる事態を想像し、シミュレーションしなければなりません。その中には、扱っているテーマの科学的な本質や、お越しいただいた方々への伝え方といった部分ではなく、イベント運営などにまつわることも多く含まれます。本来やりたいことを実現するためには、イベント運営に関わるさまざまな仕事も重要ではありますが、やはり企画の本質から外れた仕事は、単純で簡単な作業であっても精神的には堪えますね。イベント本番はそれまでに準備したことをシミュレーションに沿って粛々と実現していくというオペレーションの作業ですので、ベストなシミュレーションを実現できるように冷静に運営するように心がけています。
うれしいと思うのは先にもお話した以外にも、外部団体からさまざまな賞をいただいたり、地域密着型サイエンスコミュニケーションといえばKSELだと言っていただいたり、KSELがサイエンスコミュニケーション業界や柏の葉の地域社会、そして日本社会の中で認られつつあるのを感じるときですね。サイエンス系イベントの討論会でパネリストとして呼ばれたり、今回みたいに取材依頼が来たり、いろんな団体やメディアから話を聞きたいと思ってもらえる存在になれたのは素直にうれしいですね。
特に、日本科学未来館と上野国立博物館のサイエンスコミュニケーター養成講座の卒業生たちから勉強会講師の依頼を受けたときもうれしかったですね。日本を代表するふたつの科学館で育成された科学コミュニケーターたちがKSELの活動を学び取ろうと考えて私を勉強会に招いてくださったことは、KSELの活動を続けてきてよかったと大きな手応えを感じる節目の出来事になりました。
地域に根付いてきたと実感
──KSELという団体を立ち上げてよかったと思うことは?

もともとKSELを立ち上げる前は、地域の人たちに話を聞くと、東大のキャンパスはどんな研究をしているのか分からなくて恐い、とか、大学で研究している人は取っ付きにくいとか、距離や敷居の高さを感じる、といった感想を耳にする機会が多くありました。しかしKSELが街の中で活動を続けるにともない、大学院生や研究者も話しやすい普通の人間だ、と認識していただけたのは、地域に密着した活動を立ち上げた意義を実感した瞬間のひとつでした。それが具体的に形になった瞬間として、例えば地域の方々から、友だちと行なうお花見や自宅で行うクリスマスパーティーに来てちょっとサイエンスの話をしてよ、とお招きいただいたことがありました。こうした時には、地域に根づいてきたことを実感して、KSELを立ち上げてよかったと思いましたね。
──まさに地域密着型という感じですね。ではKSELの活動を通じて得たものは?
地域に根付いた活動の中で、街に関わる多くの方々と知り合うことができました。こうして築かれた人と人との交流やネットワークは、かけがえのない財産だと実感しています。また、技術的には、リーダーシップや企画運営に関わるさまざまなスキルを身につけることができました。KSELでは各人がリーダーシップを発揮し、1つの企画実現に向けて必要なバラエティに富んだ仕事をパラレルで進めていくというシステムなので、企画書を書いたり、予算を獲得したり、チラシを作って広報したりといろんなノウハウが身につきました。こうしたトレーニングを通じて、おおよそのイベントは実現できるという自信がつき、卒業して社会に出てもスキルとして生かせると思っています。
「マイナスからゼロへ」と「ゼロからプラスへ」

──今のKSEL、あるいは羽村さんが目指しているものは?
科学コミュニケーションには大きく分けて2つの役割があると考えていて、私はそれを「マイナスからゼロへ」と「ゼロからプラスへ」と呼んでいます。
例えば、東日本大震災に起因する原発事故後の放射能汚染に対する恐怖や、将来起こりうる巨大地震に対する不安は、程度の差こそあれ多くの方が抱いているのではないでしょうか。
しかし、分からないからと闇雲に恐れたり、デマか真実かもわからない情報に振り回されたりするのはあまり賢くないように感じます。何かが恐い、でもそのリスクを自分では理解することができないからパニックを起こしたり、誰かを批判したり、周囲の人間にまで恐怖を煽ったりするわけですが、そうではなく、恐怖に対して正面から向き合い、科学的根拠を踏まえてリスクを客観的かつ正確にとらえ、正しい恐がり方をすることが必要です。それができれば、冷静な対応が可能になり、いざという時に必要なものを準備したり避難ルートを考えたりと生き残る可能性も高くなりますし、大切な人と万が一の時の対応を相談することもできるでしょう。
他にも生活していく上でのリスクはたくさんあります。それぞれのリスクを正しく理解し、評価するときに科学が役に立ちます。冷静に自分と自分の大切な人を守るための科学的知見を知り、科学的に考え、大事な人と共有すること。それが私の考える「マイナスからゼロへ」の科学コミュニケーションです。
もう1つは、科学には夢をかなえる力があると思っています。夢は人それぞれですが、科学のことを理解していたり、科学を道具として使えたりしたら、実現に一歩近づける夢も多いと思うんですね。例えば私の場合は「宇宙人を探したい」という動機が元々あって研究者になろうとしたわけですが、その夢を叶えるためには科学の力が欠かせませんでした。他にも新薬の開発やロボットの研究などもしかりです。このような未来を作るために、先人たちが積み重ねてきた知識を学び、発展のさせ方を身につけ、そして自分や社会の夢を叶えていく力を身につける働きこそが、科学コミュニケーションのもつ「ゼロからプラスへ」の役割だと私は考えています。
夢を実現するツールとしての科学

こういうふうに、少しでも多くの人が自分と自分の大切な人を守りながら、自分の夢を叶えていくツールとしてサイエンスが一つの役割を果たしてくれたらいいなと願っています。そのためにまずはサイエンスを一人でも多くの人に身近に感じてもらいたい。それでもとっつきにくくて、敷居が高いと感じるのなら、科学を研究している科学者や大学院生を身近に感じてもらいたい。たぶん一般の人は科学者、特に大学教授などは恐いとか難しいことしか喋らなそうというイメージをもっているかもしれませんが、実際に喋ってみるとその辺の普通のおじさん・お姉さんと変わらないんですよね(笑)。
科学者のことが好きになれば何を研究しているんだろうと興味が生まれてくるし、その科学者の話を聞きたい、理解したいという思いも生まれてくると思うので、まずはそこの窓口として科学者や大学院生の姿を見せる存在にKSELはなりたいと思っています。
──3月で卒業とのことですが、卒業後のKSELとの関わり方は?
一応卒業後も関わっていくつもりではありますが、どのような形になるかはまだ模索中です。私が卒業すると初期メンバーが完全にいなくなるので、その後どうやっていくのかとても心配だから離れたくないと思う一方で、後輩たちによって作られる新しいKSELの姿を見てみたいとも思います。そもそも、誰かがいないと成り立たない組織って不健全で、それよりは誰がいなくなっても組織としてうまく回るような仕組みを考えた方がいいんじゃないかなという思いもあるんですよね。私がいつまでもいると新人がなかなか独り立ちできないという部分もありますしね。
ただ、現実問題として、これまで中心となって活躍してきた他のベテランメンバーもこの3月でごそっと卒業するので、次の世代にバトンをつなぐためにも、もう少し頑張る必要がありそうだし、5年間で培って来た地域でのネットワークやノウハウを始めとする財産を元に、さらにおもしろいことができそうな予感もしているので、今後のことは後輩たちとも相談しながらじっくりと決めていこうと思っています。

羽村太雅(はむら たいが)
1986年山梨県生まれ。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程/KSEL創立メンバー
慶應義塾大学理工学部卒業後、「宇宙人を見つけたい」との想いを叶えるため東京大学大学院 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 杉田研究室へ。専門は惑星科学、アストロバイオロジー。隕石の衝突を模擬した実験を通じて生命の起源を探る研究を続けてきた。研究の傍ら、2010年6月に柏の葉サイエンスエデュケーションラボ(KSEL)を立ち上げ、地域に密着した科学コミュニケーション活動を行なっている。その活動が認められ、日本都市計画家協会優秀まちづくり賞やトム・ソーヤースクール企画コンテスト優秀賞などを受賞。また「東葛地域における科学コミュニケーション活動」が2014年度東京大学大学院新領域創成科学研究科長賞(地域貢献部門)を受賞。さらに単独でも多様な科学コミュニケーション活動を行なっている。国立天文台定例観望会学生スタッフ、宇宙少年団(YAC)千葉スペースボイジャー分団リーダーなども務めてきた。2015年3月卒業後は起業を予定している。ちなみに名前の「タイガ」は寅年生まれに由来する。
- 羽村太雅Facebookページ
- 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ(KSEL)公式Webサイト
- 柏の葉サイエンスエデュケーションラボFacebookページ
- 理科の修学旅行他、個人での活動のページ
- 理科の修学旅行Facebookページ
初出日:2015.02.13 ※会社名、肩書等はすべて初出時のもの
